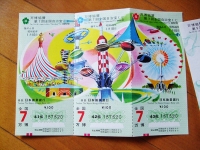2013-08-26 22:00:32
山2013その1(6月)の2日目
さて、前回の続き
28日(6月です)は、深夜に大雨の音で目覚めました
「沢の音だよ!」とかみんなで騙し合いながら重い窓を開けると、結構な雨です
4時に出発
と、宿には告げてあるので、重い腰と荷物を持ち上げ、いそいそと支度して出かけます
しっかりと雨装備して…

朝4時半頃の藤七温泉上の登山口は、視界30mというところです
寒いし。
まずは畚岳(もっこだけ)を目指してゆきます
ここは登山口からすぐで、とても見晴らしがよく
晴れていれば岩手山が一望できる、ベスト朝ご飯場所です
朝ご飯は、宿でおにぎりをにぎってもらっています
(早朝出発の客には、朝ご飯をお弁当にしてくれるのです)
さて畚岳到着

2011年の、上天気のときと
2013年の、ガスっぷり激しいときの比較画像を…
ちなみに、上の2011年画像、奥に見える美しいシルエットが岩手山です
(モデルはどちらもNくんです)
寒くて、結構な強い風のミストを喰らいながら、おにぎりを喰らいました
なんも見えないし、止まってると寒いので、どんどん進みます
陽が出てからは、主に高山植物の写真を撮ってました
ちょっと前に坦々と上がってる植物写真がそれです。

途中の谷間に大きな雪渓が残っていたりします
これは、ガスで見えない上〜の方から、ガスで見えない下〜の方まで、氷河のように続く
長い雪渓でした
これが多いと、道を失ってしまうんだよなぁ、怖い。

途中の沼も、なんだか北欧かECMのジャズのジャケ写みたいな良い雰囲気…

これの手前にはミズバショウの群生があって、けっこう日本的

記録的な大雪で、残雪どころか、かなりの倒木がありました
これなんかけっこう太いのに、めりめりと行ってる

10時頃、山荘で一休み、昼食にします
朝が早いので、昼も早いですよ
大深山荘(おおぶけさんそう)
その名の通り、かなり奥深い場所にあります

室温は15度
てことは外は12〜3度だったんかな
汗だくだけど

小屋の回りにはふきのとうがたくさん
近所には、美しい水場があります
今回は雪がかなり残っていて、花はほぼ咲いていなかったけど
斜面いっぱいに花の咲く場所から、こんこんと美しく冷たい水が湧き出ています

この上の方と手前は、雪が一面に残ってる
ラーメンとハンバーグとリゾットっていう、けっこうゴージャスな食事をとりました

さて本日後半戦
雪により、完全に道を失うので
木の上に結びつけられているピンクのリボンをたよりに進みます
雪はところどころ踏み抜いてしまうような薄さだったりするので
けっこうな注意が必要
各人1〜2回踏み抜いたりしてすっ転びました
ケガがなくってホント幸い
すごく体力奪われるんだけど…
そしてここいらの木々も、ボキボキ折れています
雪が例年になく一気に大量に積もったのでしょう…
(タクシーの運転手さんも「今年はすごい」言っていた)

橋までへし折れてた!
これは、雪でなのかと疑うほどボッキリ
それでもこのすぐ下には花が咲いている
すごい。

真っ白なで静かな森で休んで

さあいこう
余談ですが、雨装備、2人が赤青でワタシが黄緑なので
けっこういいバランスです。偶然です

シラネアオイの群生(日本固有種)

倒木と雪渓に阻まれながら、黙々と…

たま〜〜〜〜に覗く青空に、歓喜の叫びを合唱したり!
蝶も飛んでいます
一瞬の陽光でも、一気に気温が上がる!
太陽ってすごいなー

高山のバッタとかを横目で見ながら本日のピークを迎えます

小畚山(こもっこやま)
1500m弱だけど、一気に上がるので、けっこう厳しいのです

辛いとこはしょって、小畚山頂!
ここでアクシデント!
ワタシのデジカメ、死亡!
撮れるのだが、モニタが映らなくなった
2年前、同じ八幡平で一度不具合が出て修理に出したんだったなー
思えば、よくぶつけるし、湿度90%以上のところで使い過ぎです
すまんかった…
ここららは、Nくんのサブカメラを借りました
(それも落っことして、傷モノにしてしまった…!)

行く手も

背後も
霧、もや、ガス…
ほとんど自分との闘いです
午後はけっこうペースが落ちてしまい、これは今日の目的地につく頃には日が落ちちゃうぞ…なんて
焦りが出て来ました

しかし、潤う森は美しいのです…

そして、本日2度目の青空!

なんか柴犬みたいな岩

足場もけっこうな変化があり、「登山を楽しむ」にはうってつけです
日帰りは困難な位置なので、水と食料と雨具と寝袋など持参しないといけないですけど

黙々。
ところで
お気づきの方もおられるでしょうが
ほんとうに人がいない!
東北の山は、これが醍醐味ですよ
とはいえ、シーズン(7〜8月)と人気スポットはそこそこいるのですが
それでもやはり少ないです
縦走コースになると、ヘタすると1日中歩いて1人とも出会わないなんてことざらです
すなわちいろんな意味で「危険」ということでもあるのですが…
そして、けっこうクタクタとなって、そろそろ今日の目的地
そして宿泊地である三石山荘(みついしさんそう)につく頃間と思っていたところ…

結構な斜面に、延々と続く雪渓が!!
これにかなり体力を奪われる
足首は痛くなるし
ワタシは2回ほどハデに滑り落ちました(滑った先はクマザサなので、ケガはないです)
しかし手首や尻をついたので、けっこう痛かった…
他2名も1回はこけました
やはり初夏といえども東北には簡易アイゼンを持って行くべきでした…
「ムリ!」ということはないけど、疲れてるときは何が起きるかわからんからのー

朝4時過ぎから、歩く事14時間弱
18時ジャストくらいにようやくたどり着いた三石山荘
16時には着きたいってプランだったから、結構な押しです

この山荘は、周囲を沼に囲まれた、すごい潤った山荘です、水場も近いし
カエル天国!クマも出そうだけど…
日が落ちきる前に急いで夕飯の支度
すでに3名様のパーティがゴージャスな夕餉をしていたので、寝る邪魔にならないように
(山では、日が落ちたら寝る時間)
でも、先客の方々は、初めから山での食事をメインとしたハードハイクって感じの方々だったようで
割と遅くまでランタン付けて静かに酒盛りしていた

さっきまでグダグダ疲労困憊だったことなど忘れ、角煮やらドライカレーやらチョリソーやら
そしてこのときの為だけに辛い思いをして持って来た思い思いの重いビールを空け
ウヒョーー!とか言いながらカンパイ!
一気に山の夜はふけるのです…
そして深夜。
O氏がなにやらワタシの名前を呼びます
まだ真っ暗
「月が出てるよ!!」
ウヒョーーーー!!
時刻は深夜2時
外は、音が聴こえるんじゃないかってくらい満天の星空
山荘の周囲の沼では、カジカガエルが大合唱
間に挟まれる僕ら
疲労と眠気も手伝い、じわ〜〜〜っと周囲に溶け込んで行くような感覚
じーーーっと星を見ていると、ゆっくりと光源が移動している
「あれは…人工衛星だよね!?」
月の光が、濡れた山荘のトタン屋根をギラギラと照らします
カエルの声の隙間から、いろいろな静かな音が聴こえて来る…
なんともスゴイ瞬間でした
他の宿泊者の方々も、静かに外に出ていた
明日の天気は、もしかすると、もしかするかもしれない…
あと1時間半で出発の時間だ
私たちは、興奮半ば、期待と疲労に包まれて
また溶けるように眠りにつくのです。…
つづく!
(燕岳編が本年中に間に合うのか?)
28日(6月です)は、深夜に大雨の音で目覚めました
「沢の音だよ!」とかみんなで騙し合いながら重い窓を開けると、結構な雨です
4時に出発
と、宿には告げてあるので、重い腰と荷物を持ち上げ、いそいそと支度して出かけます
しっかりと雨装備して…

朝4時半頃の藤七温泉上の登山口は、視界30mというところです
寒いし。
まずは畚岳(もっこだけ)を目指してゆきます
ここは登山口からすぐで、とても見晴らしがよく
晴れていれば岩手山が一望できる、ベスト朝ご飯場所です
朝ご飯は、宿でおにぎりをにぎってもらっています
(早朝出発の客には、朝ご飯をお弁当にしてくれるのです)
さて畚岳到着

2011年の、上天気のときと
2013年の、ガスっぷり激しいときの比較画像を…
ちなみに、上の2011年画像、奥に見える美しいシルエットが岩手山です
(モデルはどちらもNくんです)
寒くて、結構な強い風のミストを喰らいながら、おにぎりを喰らいました
なんも見えないし、止まってると寒いので、どんどん進みます
陽が出てからは、主に高山植物の写真を撮ってました
ちょっと前に坦々と上がってる植物写真がそれです。

途中の谷間に大きな雪渓が残っていたりします
これは、ガスで見えない上〜の方から、ガスで見えない下〜の方まで、氷河のように続く
長い雪渓でした
これが多いと、道を失ってしまうんだよなぁ、怖い。

途中の沼も、なんだか北欧かECMのジャズのジャケ写みたいな良い雰囲気…

これの手前にはミズバショウの群生があって、けっこう日本的

記録的な大雪で、残雪どころか、かなりの倒木がありました
これなんかけっこう太いのに、めりめりと行ってる

10時頃、山荘で一休み、昼食にします
朝が早いので、昼も早いですよ
大深山荘(おおぶけさんそう)
その名の通り、かなり奥深い場所にあります

室温は15度
てことは外は12〜3度だったんかな
汗だくだけど

小屋の回りにはふきのとうがたくさん
近所には、美しい水場があります
今回は雪がかなり残っていて、花はほぼ咲いていなかったけど
斜面いっぱいに花の咲く場所から、こんこんと美しく冷たい水が湧き出ています

この上の方と手前は、雪が一面に残ってる
ラーメンとハンバーグとリゾットっていう、けっこうゴージャスな食事をとりました

さて本日後半戦
雪により、完全に道を失うので
木の上に結びつけられているピンクのリボンをたよりに進みます
雪はところどころ踏み抜いてしまうような薄さだったりするので
けっこうな注意が必要
各人1〜2回踏み抜いたりしてすっ転びました
ケガがなくってホント幸い
すごく体力奪われるんだけど…
そしてここいらの木々も、ボキボキ折れています
雪が例年になく一気に大量に積もったのでしょう…
(タクシーの運転手さんも「今年はすごい」言っていた)

橋までへし折れてた!
これは、雪でなのかと疑うほどボッキリ
それでもこのすぐ下には花が咲いている
すごい。

真っ白なで静かな森で休んで

さあいこう
余談ですが、雨装備、2人が赤青でワタシが黄緑なので
けっこういいバランスです。偶然です

シラネアオイの群生(日本固有種)

倒木と雪渓に阻まれながら、黙々と…

たま〜〜〜〜に覗く青空に、歓喜の叫びを合唱したり!
蝶も飛んでいます
一瞬の陽光でも、一気に気温が上がる!
太陽ってすごいなー

高山のバッタとかを横目で見ながら本日のピークを迎えます

小畚山(こもっこやま)
1500m弱だけど、一気に上がるので、けっこう厳しいのです

辛いとこはしょって、小畚山頂!
ここでアクシデント!
ワタシのデジカメ、死亡!
撮れるのだが、モニタが映らなくなった
2年前、同じ八幡平で一度不具合が出て修理に出したんだったなー
思えば、よくぶつけるし、湿度90%以上のところで使い過ぎです
すまんかった…
ここららは、Nくんのサブカメラを借りました
(それも落っことして、傷モノにしてしまった…!)

行く手も

背後も
霧、もや、ガス…
ほとんど自分との闘いです
午後はけっこうペースが落ちてしまい、これは今日の目的地につく頃には日が落ちちゃうぞ…なんて
焦りが出て来ました

しかし、潤う森は美しいのです…

そして、本日2度目の青空!

なんか柴犬みたいな岩

足場もけっこうな変化があり、「登山を楽しむ」にはうってつけです
日帰りは困難な位置なので、水と食料と雨具と寝袋など持参しないといけないですけど

黙々。
ところで
お気づきの方もおられるでしょうが
ほんとうに人がいない!
東北の山は、これが醍醐味ですよ
とはいえ、シーズン(7〜8月)と人気スポットはそこそこいるのですが
それでもやはり少ないです
縦走コースになると、ヘタすると1日中歩いて1人とも出会わないなんてことざらです
すなわちいろんな意味で「危険」ということでもあるのですが…
そして、けっこうクタクタとなって、そろそろ今日の目的地
そして宿泊地である三石山荘(みついしさんそう)につく頃間と思っていたところ…

結構な斜面に、延々と続く雪渓が!!
これにかなり体力を奪われる
足首は痛くなるし
ワタシは2回ほどハデに滑り落ちました(滑った先はクマザサなので、ケガはないです)
しかし手首や尻をついたので、けっこう痛かった…
他2名も1回はこけました
やはり初夏といえども東北には簡易アイゼンを持って行くべきでした…
「ムリ!」ということはないけど、疲れてるときは何が起きるかわからんからのー

朝4時過ぎから、歩く事14時間弱
18時ジャストくらいにようやくたどり着いた三石山荘
16時には着きたいってプランだったから、結構な押しです

この山荘は、周囲を沼に囲まれた、すごい潤った山荘です、水場も近いし
カエル天国!クマも出そうだけど…
日が落ちきる前に急いで夕飯の支度
すでに3名様のパーティがゴージャスな夕餉をしていたので、寝る邪魔にならないように
(山では、日が落ちたら寝る時間)
でも、先客の方々は、初めから山での食事をメインとしたハードハイクって感じの方々だったようで
割と遅くまでランタン付けて静かに酒盛りしていた

さっきまでグダグダ疲労困憊だったことなど忘れ、角煮やらドライカレーやらチョリソーやら
そしてこのときの為だけに辛い思いをして持って来た思い思いの重いビールを空け
ウヒョーー!とか言いながらカンパイ!
一気に山の夜はふけるのです…
そして深夜。
O氏がなにやらワタシの名前を呼びます
まだ真っ暗
「月が出てるよ!!」
ウヒョーーーー!!
時刻は深夜2時
外は、音が聴こえるんじゃないかってくらい満天の星空
山荘の周囲の沼では、カジカガエルが大合唱
間に挟まれる僕ら
疲労と眠気も手伝い、じわ〜〜〜っと周囲に溶け込んで行くような感覚
じーーーっと星を見ていると、ゆっくりと光源が移動している
「あれは…人工衛星だよね!?」
月の光が、濡れた山荘のトタン屋根をギラギラと照らします
カエルの声の隙間から、いろいろな静かな音が聴こえて来る…
なんともスゴイ瞬間でした
他の宿泊者の方々も、静かに外に出ていた
明日の天気は、もしかすると、もしかするかもしれない…
あと1時間半で出発の時間だ
私たちは、興奮半ば、期待と疲労に包まれて
また溶けるように眠りにつくのです。…
つづく!
(燕岳編が本年中に間に合うのか?)